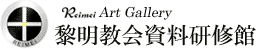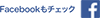沿革
| 2015年 | 琳派400年記念「小さな琳派展」を3期にわたって開催(5月3日~10月18日) 総入館者数が100,000人に到達(8月2日) |
| 2014年 | 京都市博物館連続講座第4回を「京都と琳派の美」と題して当館で開催(1月24日) |
| 2013年 | 春の茶会開催(3月20日) 琳派展I(5月~6月)II(9月~10月) 生花展および写真展を第8室にて開催(夏季美術展の一環)(7~8月) 総入館者数が80000人に到達(9月13日) |
| 2012年 | 総入館者数が60000人に到達(1月12日) 亀岡末吉の装飾展開催(第8室)(3~6月) 生花展開催(夏季美術展の一環として)(7~8月) 佐伯道之コレクション展開催(第8室)(11~12月) |
| 2011年 | 京都市内博物館施設連絡協議会総会を当館で開催(7月8日) 中村史朗滋賀大教授講演「書の魅力」(7月8日) 特別展「宗達から光琳へ 水墨画を中心に」開催(9月) |
| 2010年 | 特別展「本阿弥光悦 書と蒔絵」開催(9月) ギャラリーコンサート開催(1月) 年間入館者が10000人を超える |
| 2009年 | 京都ミュージアムロードに協賛(以降毎年) 市教委養成のボランティア「虹の会」導入開始 NHK京都カルチャーセンター(中村昌生氏)現地研修(5月25日) 京都知恵博に協賛 特別展「開館5周年記念リクエスト展」開催(9月) 中部義隆氏(大和文華館)講演「光琳芸術の魅力」(9月23日) 関西文化の日に協賛(以降毎年) |
| 2008年 | 京都市内博物館施設連絡協議会(京博連)に 正会員として加盟承認 |
| 2005年 | 陳列品の解説を学芸担当者が始める 関西照明技術普及会賞受賞 |
| 2004年 | 資料研修館開館(9月23日) 美術研修会を資料研修館で開催 (以降毎年1~3回開催) |
| 1984年 | 山崎重久氏講演「岡田茂吉師と芸術」(12月23日) |
| 1983年 | 美術資料室をボストン美術館理事一行訪問 |
| 1982年 | 美術資料室開室 |
| 1974年 | 美術品の収集をはじめる |
| 1970年 | 美術研修会始まる (以降毎年2~5回美術鑑賞会開催) |
メディアでの紹介
| 2015年 | 琳派400年記念祭イベントガイドで紹介 「琳派」最速入門(和楽ムック)で琳派に出会える美術館として紹介(2月5日) てんとう虫/Express(5月号)で琳派展紹介 クラブ・コンシェルジュ第37号で「ニッポンの贅と美」として特集記事・特別見学会開催(5月30日) |
| 2014年 | 読売新聞京都版に展覧会紹介記事(5月15日) |
| 2013年 | ガイドブック「京都ミュージアム探訪」で紹介(京博連・京都市教委 3月発行) GINZA(3月号)に琳派作品を見られる美術館として紹介 週刊トマト&テレビ京都「博物館の至宝」で紹介記事(11月) |
| 2012年 | My Kyoto(京都市発行)2012年秋号に紹介記事 和楽(小学館発行)10月号に紹介記事掲載、表紙は当館所蔵の鹿楓蒔絵小箱。(9月1日) サヴィ(SAVVY)3月号に紹介記事掲載(1月23日) |
| 2011年 | KBS京都テレビ「ぽじポジたまご」に出演(9月6日) ガイドブックレット「京発見!ミュージアムへ行こう」で紹介(10月発行) |
| 2010年 | 週刊トマト&テレビ京都「おもしろ探検」に紹介記事(7月2日) 毎日新聞「京都ミュージアム案内」に紹介記事(11月11日) |
| 2009年 | 「京の博物館」(42号)で紹介(1月) KBS京都テレビ「ぽじポジたまご」に出演(11月17日) |
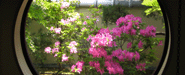
施設概要
RC造3階建
のべ床面積 1459㎡
陳列室 10室
開館 2004年9月23日
のべ床面積 1459㎡
陳列室 10室
開館 2004年9月23日